◆「特例法」の憲法問題
特例法による天皇退位に、憲法上の問題はないのか?
<朝日新聞>
上の記事を参考にしながら、今後の動きをチェックすることにした。
<毎日新聞>
シリーズ・退位 国会対応まとまる
毎日新聞
違憲の疑義、避けるべきだ
木村草太・首都大東京教授 
衆参両院の正副議長の見解は、皇室典範の付則に特例法と皇室典範は一体であると書き込むとしている。実質的な内容は国会の議決で退位できるという皇室典範改正になっているので、屋上屋を架しているという印象を受ける。
特例法では、天皇陛下が退位するとしか規定されないだろう。それでは、退位の理由が明確にならず、将来、強制的な退位や恣意(しい)的な皇位の継承を招く可能性がある。高齢で、執務が困難になってきているという今回の事情は、他の天皇にも生じ得る話だ。法は、同じ状況にある者に公平に適用されるべきであり、一代限りの特例法は好ましい選択肢ではない。
憲法2条は「皇位は皇室典範の定めるところにより継承する」と定めている。この文言を理由に、皇室典範に基づかない退位は憲法2条違反と考える専門家もいる。私自身は特例法による対応が許される場合もあると考えるが、違憲の疑義が生じる皇位の継承は避けるべきだし、今回あえて特例法にする必要がない。
現在の皇室には、皇位継承資格者があまりにも少ない。見解は女性宮家の創設などについて触れているが、皇位の安定的継承を考えるのであれば、退位を認めるのと同時に、女性・女系天皇を認めるべきだろう。約70年前に皇籍離脱した人を、男系であるという理由で皇族に戻したとしても、天皇としての正統性を獲得できるかと言うと、相当難しい。退位と同時に女性・女系天皇を認めるかどうかの結論を出した方がいい。皇太子殿下が天皇に即位する時点で、長女の愛子さまの地位が定まっていることが、理想的だ。女性・女系天皇の議論は相当熟していると思われるから、先送りするなら相当の理由を示す必要がある。どうしても無理なら、退位と女性・女系天皇などを2段階に分けて検討する可能性もあろう。
象徴天皇制については、憲法4条で「国政に関する権能を有しない」と定めている。天皇は個人的に政治的見解を表明したり、政府の法案に反対したりできない。天皇の公的行為については、政治的権能でない範囲で行われる。その時の内閣が責任を持って、公的行為はどの範囲で行うのかを天皇と相談して考えていくべきだと思う。
次の天皇が天皇陛下のように積極的に被災地訪問などをすべきだと考えることもあり得るし、軽々しく外に出て行くべきではないと考えて、ほとんど公的行為をしなくなることもあり得る。象徴天皇のあり方は一つではないので、それぞれの天皇で、公的行為についての考え方が違って当然だと思う。【聞き手・南恵太】
国論の分裂、強めない意義 井上寿一・学習院大学長
一代限りの特例法で退位という今回の結論は、事態の緊急性と長寿社会化の進展という条件を考慮すればやむを得ない。与野党が大筋合意したことは、皇位継承に関する問題で国論を二分した前例を作らなかった点で、評価できる。
ただし、天皇と前天皇が同時にいると、いわば「権威の二重化」が生じやすくなる。また、このままだと、同じ事態は将来も起きるだろう。今回は緊急で議論の方法も他になかったが、これから、全国民が当事者意識を持てる形で、皇位の安定的な継承の方法、さらに、今の時代にふさわしい象徴天皇制のあり方について議論を深めなければならない。
天皇陛下の退位を巡る政府の有識者会議のヒアリングで、もっとも説得力があったのは、笠原英彦・慶応大教授の「天皇と前天皇が共存すると国民の混乱を招きかねず、憲法が定める象徴としての国民統合の機能が低下するおそれがある」という意見だった。
その笠原教授も、天皇が国事行為をできなくなった場合に摂政を置く可能性は否定しなかった。摂政が置かれる期間が長期化しても権威の二重化が起きないようにする方策は、具体的に示せなかった。そうであれば、結局のところ、今の陛下が否定されている摂政よりは、退位の方がまだよいと言わざるを得ない。
陛下が摂政を置くことに否定的なのは、大正時代の前例があるからではなかろうか。大正は、デモクラシーと協調外交の平和な時代として振り返られがちだが、大正天皇は病弱で、大正10(1921)年に裕仁親王(後の昭和天皇)が摂政となる直前、皇室を巡る大きな問題が二つも起きた。
一つ目は、裕仁親王と久邇宮良子(くにのみやながこ)女王(後の香淳皇后)の結婚に元老の山県有朋らが反対した。この件は、「宮中某重大事件」として新聞で報道されて、国民を巻き込んだ大問題になった。もう一つ、山県が推進した裕仁親王の訪欧に貞明皇后らが反対した。
大正天皇が健康であれば、どちらも天皇の差配で事態はすぐ収拾しただろう。今の陛下は、昭和天皇から直接、大正時代の話を聞いて、「健康で判断力がある天皇がいないと皇室は安定せず、国民も動揺する」と教わられたのではないかと想像する。
今回は、「陛下は安倍晋三首相に抗議して退位される」などと解釈する人もいた。この解釈は、悪く言えば、国論を二分する問題の道具に皇室を使う「天皇の政治利用」だ。国会が大筋まとまったのは、国論の分裂をこれ以上強めない意義がある。
戦後、今の皇室制度になった当初から、皇位の安定的な継承が難しくなる可能性は分かっていたはずである。それなのに陛下ご自身にテレビでお話しいただくことになったのは、戦後歴代内閣の責任だ。しかも、そのテレビの視聴率が特別に高いとは言い難かった。
課題は、権威の二重化を避ける方策や同じ問題が起きた際への対応に限らない。皇室典範改正などだけで答えが出ない、これからの時代にふさわしい象徴天皇制のあり方を、国民全体で深く考えてゆくべきだ。【聞き手・鈴木英生】
特例法を先例に要件作りを 高橋和之・東京大名誉教授

憲法上天皇の退位は禁止されておらず、退位を認めるために皇室典範を改正することも、特例法を定めて対応することも許容されている。どちらを選ぶかは政策判断だ。ただ、典範改正にあたり退位の要件を定めるのは相当難しく、先例を重ねて、法文を考える方がうまくいくのではないだろうか。
皇位継承は「皇室典範の定めるところによる」と憲法2条に書いてある。憲法が制定された当時、皇室典範がどう理解されていたかというと、「国会が議決する」としたところに力点はあった。国会が決める法律で定めるということだ。明治憲法下の皇室典範は憲法と対等な地位にある独自の法規範で、議会の関与が及ばなかった。現憲法は、皇室典範自体に重きを置いたものではないという解釈が成り立つだろう。それでも憲法に典範と書いているから尊重するというなら、典範の本則に書いてもよい。だが、本則に書かないから違憲とまで考える必要はない。
退位が政治的な意味を持たないようにしなければいけない。憲法上、象徴としての天皇が行う行為は国事行為のみと理解すべきである。それ以外の行為も許されてはいるが、それができないことを理由に退位の制度を作れば象徴天皇制の理解を変えることになる。
今の天皇陛下は、象徴としての天皇が憲法上どういう形で存在し得るかを、長年考えてこられた。そして国民に寄り添うという結論に到達したのだろう。だが、被災地の慰問や戦地の慰霊などの公的行為は法的な義務ではない。陛下の真心によるものだ。公的行為の範囲は明確でないし、状況が変われば違う形になることもあろう。
退位を検討する際、天皇の意向を知る必要はある。だが、「退位は天皇の申し入れに基づく」などと曖昧にすると、天皇は「国政に関する権能を有しない」という憲法4条との問題が出てくる。いつでも退位を申し出られるように読め、政治利用されやすいからだ。「80歳になれば、天皇は退位を申し出ることができる。申し出を受け、国会で議論し決定する」と書けば中立的かもしれない。それでも将来、米国のように年齢差別が問題になる可能性はある。
法のありようには二つの大きな考え方がある。一つは、最初から法律で定めるヨーロッパの大陸法的な法思想だ。もう一つの英米法は、先例を積み重ねる中で次第にルールを形成する。大陸法の考え方では、後は法律を適用するだけだから政治的問題になりにくい。しかし、その時点で先を見通した法律を作るのは容易ではない。今回の対応はいずれにしろ先例になる。先例を巡る議論を重ねる中から、国民が納得できる要件が固まってくるのではないか。その都度国会で議論して認めるかどうかの結論を出す方が、天皇の地位は「国民の総意に基づく」という憲法に合うとみることもできる。
最後に、議会外で各党の意見を集約するやり方は、あまり好ましくないことを指摘しておきたい。国民に開かれた本会議で扱うべきだからだ。皇位の安定継承に向けた検討は、今後も国民の後押しがないと進まないだろう。【聞き手・岸俊光】
特例法と典範は一体
衆参正副議長の見解は、特例法の名称を「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」と定め、典範付則に特例法と典範は一体と明記するよう求めている。これにより、皇位継承は典範によるとした憲法2条に違反するとの疑いを免れ、退位は例外的な措置で、かつ将来の先例になるとした。また、女性宮家創設など安定的な皇位継承について、政府に速やかな検討を求め、結論時期について付帯決議に盛り込むよう各党の合意を促している。
毎日新聞




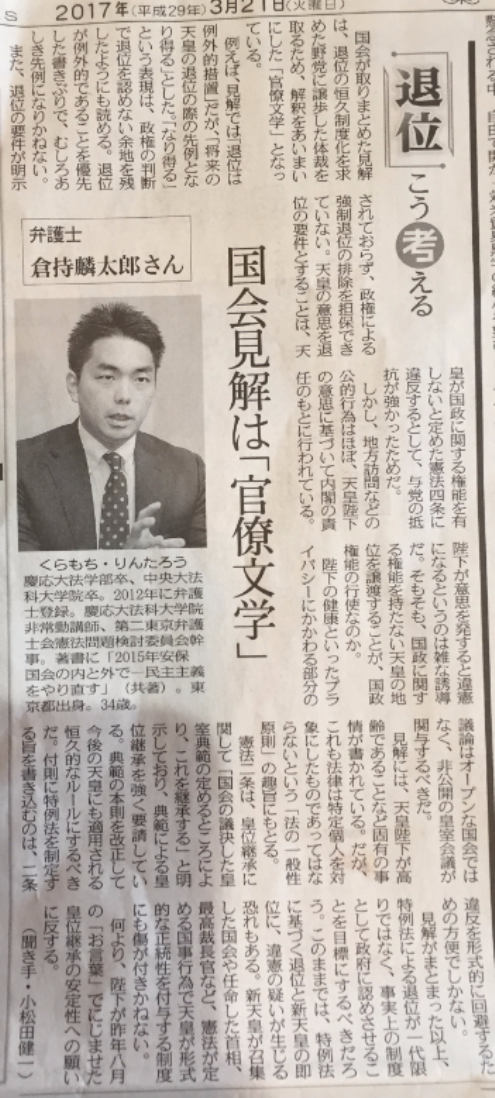





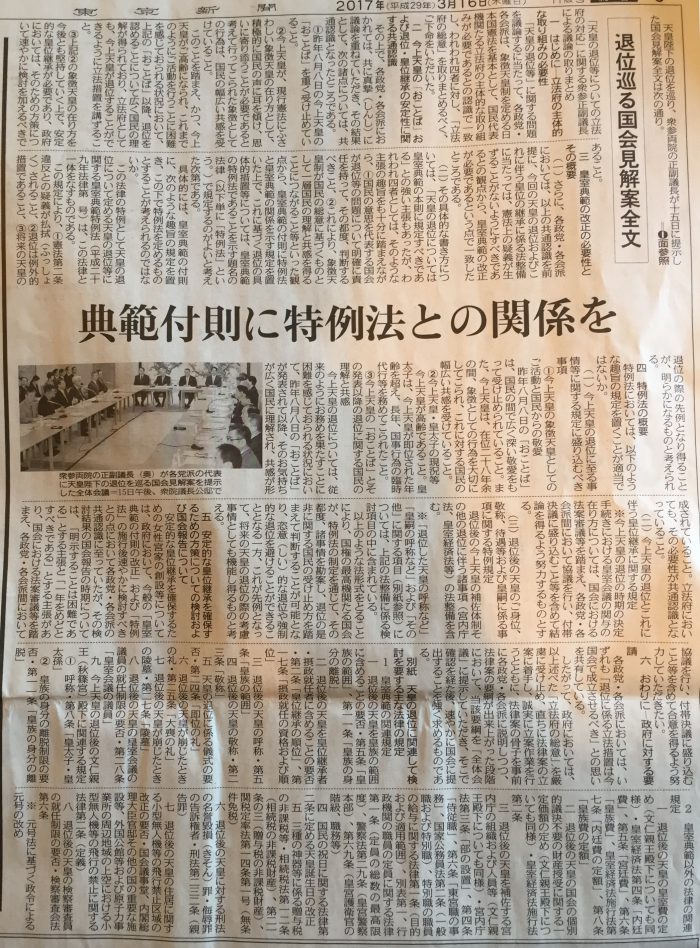

 小松耕輔さん(1884-1966)(へぇ、こんな人だったんだ)
小松耕輔さん(1884-1966)(へぇ、こんな人だったんだ)